
「介護のために離職した介護のプロ」からもらったハガキ。
「やはり介護は家族がやるべきなのか?」という問いかけを、ここに書いていく。
介護のプロが、介護離職をした話がある
ハガキが一枚、届いた。
父が入所している介護施設からのものだ。
施設からハガキが来るのはあんまりない。
差出人は、なんと施設長だった。
パソコンで打たれた小さい字がハガキにびっしり書かれている。読んだ。とてもショックなことが書かれていた。
「家族ふたりの介護に専念する必要があり、
退職しなければならなくなりました」
苦渋の選択だった、と続いていた。
「介護のプロ」でさえも離職を選ばざるを得ない
施設長は、介護の現場を長く知っている人だ。
制度を理解し、現場を回し、家族の事情にも触れてきた人だと思う。
その人が、
「家族の介護のために、仕事を辞める」
そう書いてきた。
この一文が、私の胸倉をつかんだ。介護のプロでさえも家族介護のための離職は避けられないことに、私はいたたまれなくなった。
サービスあれども離職は起きる
介護の話をすると、決まって言われることがある。
「ケアマネさんに任せたらいいじゃない」
「ヘルパーさんをもっと使えば?」
「介護にのめり込んだらダメだよ」
私も、何度も聞かされてきた。
たしかに、正論だ。
介護には、制度もある。サービスもある。確かにそうだ。
でも、このハガキを前にして、思った。
それが「成り立たない」こともある、ということを。
制度を熟知していても、サービスを使いこなせても、家族介護は避けられない、ということを。介護のプロである施設長が離職するのだ。
制度を熟知し、
家族を任せる側の気持ちも、
現場で起きている現実も、
そう、介護のすべて知っていた施設長――
そんな彼が、仕事を辞めざるを得ない。
介護のプロフェッショナルですら、家族介護のための仕事を辞めるのだ。この事実は重い。
介護には家族にしかできない部分がある
介護サービスは、夜間・早朝には来てくれない。
認知症者は、朝起きると冷蔵庫を開けて中の物を食べている場合がある。そんな事態には家族が対応しなければならない。
病院・施設に預けることができても、家族の誰かがキーパーソンを担うことになる。
キーパーソンは、判断の重さ、責任そして義務感を背負うことになる。
そればかりか金銭の支払い、預貯金の管理、手続き、施設との話し合い、膨大な書類の山……などなどに向き合うのだ。
介護しなければわからない経験を、家族は日々、味わう。そして苦しむ。
苦しむ。
これは制度・サービスでは代行できない。
介護離職は、個人の問題ではない
介護離職は、
「その人ががんばりすぎたから」
「助けを求めなかったからだ」
そう語られがちだ。
でも、本当にそうだろうか。
制度を知っていて利用できる人でも、最後には「辞める」しか残らない現実がある。
それは、個人の問題ではなく、構造の問題ではないか。
誰だって個人的な愉しみを謳歌したい。親が要介護状態であっても、娘・息子・配偶者は自分の人生を生きたい。やりたい仕事をやりたい。そんな想いを担保するのが制度だと思うのだが、そんなふうに制度はできていない。
つまり介護離職は個人のやりくりに期待できず、構造が人を離職という選択しかないように向かわせるのだ。
いつの間にか変わった、この国の前提
かつて、この国の国是といえば「専守防衛」だった。
少なくとも、建前としてはそう語られてきた。
けれど、介護の現場を見ていると、
別の国是があるように感じる。それが、「家族介護」だ。
誰も明言しない「親の介護は家族がやるもの」という前提――
法律に書いてあるわけではない。
誰かが公式に宣言したわけでもない。
けれど、困ったとき、最後に引き受けるのは家族。
制度が途切れたところを埋めるのも家族。
断る自由は、最初から用意されていない。
一枚のハガキが教えてくれたこと
施設長からのハガキは、
「特別な誰かの話」ではない。
むしろ、
制度を知り尽くした「介護のプロ」ですら、ここに行き着く
――その現実を、静かに突きつけてくる。
介護離職は、
この国で生きている限り、
誰の身にも起こり得る話だ。
「まずは家族がみてくださいね」
「その程度の要介護では施設に入れないですね」
「夜間は訪問介護してないんです」
「徘徊には気をつけてあげてくださいね」
親の介護を前にして、娘・息子・さらには奥さんに逃げ場がなくて、待ったなしなのだ。
「家族介護は当たり前なのか?」
自分の時間を削りながら、私はその問いから離れられずにいる。


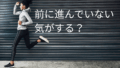
コメント